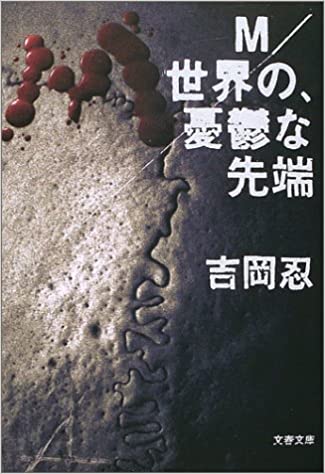
■体感する
■002. 奈良市中央公民館「ヒロシマ原爆展」と宮崎勉 (2003.8.5)
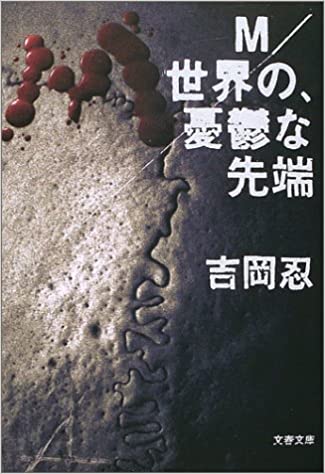
そんなわけで今日(木曜)は朝からバイクで西大寺の事務所へ行き、チビの入園で必要な私の就業証明を書いてもらってから、奈良の三条通りにある市立中央公民館へ立ち寄った。前日の新聞で目をとめたのだが、奈良市と広島市が共催する「ヒロシマ原爆展」 を覗きに行ったのだった。初日のオープニング・セレモニーで、県内の演奏家によるミニ音楽会を聴いた。のっけから女性四人による「さとうきび畑」の歌がこ ころに沁みて堪らなかった。それから、13歳の女学生のときに被爆をして現在、広島の平和記念資料館で語り部をされているという71歳の女性の一時間に及 ぶお話。収容先で再会した顔の皮がずるりと垂れ下がった同級生たち(彼女らはすべて翌日までに死んだ)。祖母が持ち帰ってきた母と妹の遺骨。原爆症のため にその後自殺した父親。「こうした話ができるようになるのに50年かかりました」 それから展示会場へ移り、さまざまな原爆資料を見て回った。熱線を浴び て痘痕面のようになった瓦。どす黒く伸び続けた異形の爪。ひとりでは可哀相だからと子どもの亡骸と裏庭に埋められ、40年後に掘り出された三輪車。足の影 が映った形見の下駄。被爆して死んでいった子どもらが身につけていたズボンやワンピースやゲートル。遺体が抱きかかえるようにしていた、食べることなく炭 化した母親の手弁当。私はいまだ、ヒロシマを訊ねたことがない。作家の辺見庸は自身の講演会で、アフガニスタンから自ら拾い持ち帰ってきた米軍のクラス ター爆弾の「飴のように溶け曲がった」破片を会場内に回した。「爆弾というもののマチエールというか触感を私は説明したかったのだ。戦争が抽象化され血抜 きされて語られることに対し、どこまでも冷たい死の質感で反駁したかった」と、かれは言う (いま、抗暴のときに・毎日新聞社)。私は、そのようなモノに会いに行ったのだ。腐ったことばなど突き 抜けて無言で迫ってくる、そのようなモノとおのれを対峙させたかったのだった。これは過去ではない。アフガニスタンやイラクではいまもこれらの地獄絵のな かで人々が、無辜の子どもたちが、尊厳を奪われた虫けらのように殺され泣き叫び続けている。そして私たちの奇妙に倦んだ日常のディティールはそんな狂った ような世界の上にだらりと乗っかっている。かなしみの中から怒りがこみ上げてくる。怒りのうちに痛苦がある。それらはやがて得体の知れぬ吐き気となって、 臓腑に満ちた。私はそれ以上堪えきれず、のろのろとした足取りで公民館を出てきた。
広島平和記念資料館WebSite http://www.pcf.city.hiroshima.jp/index2.html
広島平和記念資料館バーチャル・ミュージアム http://www.pcf.city.hiroshima.jp/virtual/index.html
2003.8.7
昨日の「ヒロシマ原爆展」では、若い人の姿はほとんど見かけなかった。あの戦争を体験した世代の年寄りたちで会場は埋め尽くされ、きっと県内の広 島県人会のような団体も呼ばれていたのだろう、語り部の老女の話を聞きながら涙ぐんでいる姿もあった。「記憶」ということを思う。肉体に刻まれた拭い難い 記憶。そのような意味において、人の肉体というものは脆いものだ。この国では、もう直にあの悲惨な時代の記憶など萎んだ綿菓子のように霧散してしまうので はないか。いやすでに霧散しかけているのではないか。「M / 世界の、憂鬱な先端」(文春文庫) の中で吉岡忍は、4人の少女を殺害した宮崎勤という人間の中で歴史認識というものが見事なまでに欠落していたことを指摘している。宮崎は精神鑑定の鑑定人 との対話のなかで、真珠湾や長崎・広島に投下された原爆のこともおろか、日本がかつてアメリカと戦争をしたことさえ知らぬような受け答えをしている。それ は単に、かれ一人の個人的な無関心にだけ帰結され得るものなのだろうか。上野の美術館で見た黒い穴のような19世紀のある絵画と中国における日本の人体実 験に触れたある文章のなかで辺見庸は「19世紀の闇がハルビンと山西省の闇を結び、いまに流れこみ、記憶の再生を誘う。忘却を怒る。アナムネーシス(想 起)を無言で呼びかける」と記す。作家はその短文に次のような歌を寄せている。「灯を消したたまゆら闇はわが顔を死者のてのひら包むごと冷ゆ」(鈴木幸 輔・花酔)
宮崎勤のことを考えている。考えるというより、千尋に寄り添う哀れな顔ナシの如く私の背(せな)にうっすらと、だが濡れたTシャツのようにべたりと重く貼りついているような心地がする。たとえば、作家が描く次のような瞬間。
私は宮崎勤がこの時期、精神の決壊を起こしていたと思う。
祖父が倒れ、亡くなって以後にはじまった遺骨を食べる行為、家人や親戚に対する暴言と暴力が示すものは、精神の決壊以外にないと考える。彼は自己をまとめ上げ、統合する力を失い、ハザードを起こし、その勢いを止めることができなくなった。
思えば、よくここまで持ちこたえてきた。彼は幼児のころから手のひらを上げて、ちょうだい、をする ことができなかったから、身近な者たちに甘えたり、親愛な意思や感情を通わせる経験をしないまま成長した。友だちと遊ぶ年頃には、手首のことを気づかれ、 いじめられるのではないかとびくびくしつづけた。集団への適応を当然と考える学校教育は、そこに拍車をかけるばかりだった。取り残されたくない、周囲にさ れたくないと思った高校から短大にかけての数年間、彼は流行っているものに夢中になることで現実に適応しようとした。それはうまくいきそうに見えた。だ が、もともと歴史を切断し、現在と未来しか視野に入れないことで成り立ってきた戦後日本社会に生まれたサブカルチャーは、さらにその現在のリアリティーか らも浮遊し、忘却と新奇をせわしなくくり返す消費社会に巻き込まれていく運命にあった。
これらひとつひとつの節目で、宮崎は綱渡りをした。どれだけそのことを自覚していたかどうか、いま となってはよくわからない。ただタイトロープの上でバランスを崩しそうになると、セーフティーネットのように甘い世界があった。甘い世界にいけば、祖父や 鷹にいが自分をつつみ込んでくれる。そのことを彼は知っていたし、まわりも彼が祖父の部屋に入りびたっていたことに気がついてはいた。
しかし、鷹にいがどこかに連れ去られ、いま祖父もいなくなった。甘い世界は、からっぽだった。
精神が決壊する。
真夜中の墓場に行って骨壷を開け、骨を食べる。暴力や暴言がはじまる。周囲の人たちに目撃された異 様な行為は、ここを境にはじまっている。私は、それ以前が正常だった、と言いたいのではない。正常と異常のあいだで揺れ動く葛藤やあせりや自覚、なんとか しようという気持ちと、祖父が作ってくれた甘い世界によって、かろうじてここまで持ちこたえてきた精神のまとまりが、ここで決壊したということ。生活史を たどってくれば、その軌跡が浮かび上がる。
(中略) 私はいま、精神を決壊させ、ばらばらになりながら、あっというまに濁流に飲み込まれていく宮崎勤の姿を見ている。
「M / 世界の、憂鬱な先端」(吉岡忍・文春文庫)
4人ものいたいけな幼子を無惨な死に至らしめた宮崎勤という存在とこの私はどれだけ離れているといえるだろうか。どこかで歯車のひとつが狂ってい たらじぶんもかれのようになりはしなかったと果たして言い切れるだろうか。私は、じぶんがこれらの光景と無縁だとはとても思えない。私はいまだ、ときに無 明の穴ぐらへと堕ちてしまいそうになる。雨戸を閉め、逮捕時のニュースで流れた宮崎勤の部屋のような空間へ己を閉じこめ、誰とも顔を合わせたくなくなる。 いびつな穴ぐらのなかで、いつしか澱んだ空想を育み増殖させ始めたかも知れない。
ただ私とかれの間で決定的に違うのは、私の場合、常に私という不確かな存在を対象化して客観視させてくれる〈他者〉の存在があったということだ。 それはときに腐れ縁の悪友たちであったり、ディランやレノンなどの音楽であったり、妻や娘の存在であったりしてきた。それらが私を、私がみずからを見失い そうになったとき、かろうじてこの世界の端につなぎ止めてくれた。私はかれらの〈眼〉によってみずからの存在を笑い、疑い、突き放し、信頼し、もういちど 確かめなおすことができた。世界とのバランスを取り戻すことができた。宮崎勤に悲しくも欠けていたのは、そのような〈他者〉の存在ではなかったかと思う。 人はたったひとりでおのれという存在を支えきれぬ瞬間もある。娘が投げかけてくる無邪気な笑顔を前にして、私はときにはっと目を覚ます。夜更けに静かな寝 息をたてているつれあいのぬくもりにそっと身を寄せて世界の切れ端をつかむ。
清志郎がかつてのオーティス・レディングのバックバンド MG'S sと共にメンフィスで録音したアルバムの中に「世間知らず」という曲がある。私はこの曲を、もし叶うことならば、独房でいまはただ蝉の抜け殻のように死刑 を待つだけの宮崎勤に聴かせてやりたい。そしてかれに言ってやりたい。このような夢の見方もできたのではないか。ひょっとしたらそんな別の人生もあり得た のではなかったか、と。いまにしてはすでに何もかもが遅すぎるが、それでも言ってやりたい。
そしてもちろん、私は相変わらずその道を歩き続けるのだ。ときには暗い無明の穴ぐらに足をとらわれながら夢をまだ見てる。
大型の台風10号が迫りつつある深夜に
2003.8.8
「M / 世界の、憂鬱な先端」の宮崎勤の項をやっと読了する。最終章の酒鬼薔薇事件に関する130頁余がまだ残っているが、ちょっと息継ぎをしたい気分だ。
精神を決壊させ暗い濁流に呑み込まれていった宮崎勤は、まさに急斜面を転がり落ちていく無明の闇と化す。4人目の少女の殺害にいたってかれは、少 女の遺体の頭部及び手足を切断してその血を呑み、手首を焼いて喰らい、のちに杉林に放置して白骨化しかかっていた蛆にまみれた頭蓋を洗う。そこで不思議 な、何ともいえぬ静謐でいて凄惨な場面が立ち現れる。かれは洗った少女の頭蓋骨を抱いて奥多摩の人気のない山道をのぼっていく。そこは「子どもの頃、おじ いさんとピクニックをした甘いところ」で、かれはとある木の根元に腰をおろし、車の座席にあったスナック菓子を食べ、子どもの頃にテレビで見た「ひょっこりひょうたん島」の歌をうたった。
その「ひょっこりひょうたん島」について、吉岡忍は原作者の井上ひさしがずっとのちになって明かした次のような話を紹介している。
井上は語っている。ひとつは、「この物語には親が存在しないこと」 そう 言われてみればたしかにあそこには父親、母親、両親、そういう役割の登場人物は一人も出てこなかった。子どもも大人もひとりひとり、自分のキャラクターで 立ち、動き、生きている。物語全体が子ども世界のユートピアを描いていた。
そのようになった理由のすべてを説明するわけではないだろうが、井上は原作者二人ともが、また担当 ディレクターも、両親にたよれない子ども時代を過ごした、という共通の体験があったことを打ち明けている。だから、あそこで「大人たちに絶望した子どもの 明るさ」を描こうとしたのだ、と。
もうひとつは、あの登場人物たち全員が、「じつは死んだ子どもたちです。それは現実問題をクリアして、あの時間にユートピアを求めた。ユートピアとはどこにもない場所で、それを「ひょっこりひょうたん島」に求めたのです」
死んだ子どもたちの世界だったからこそ、あの島には食糧問題が発生しなかった。その上で、親や大人 に絶望した子供たちの明るさ、死んだ人の明るさを描いてみること、それが二人の原作者のひそかな狙いだった、と井上は言う(2000年9月、山形県川西 町・遅筆堂文庫生活者大学校「ひょっこりひょうたん島」講座での発言)。
「M / 世界の、憂鬱な先端」(吉岡忍・文春文庫)
「手のこと(障害)に気づいていない小さいころ。知らないころにもどりたい」
「(女の子が)ひとりぼっちの姿を見て、自分の姿を見てしまうんだ。自分の手に気づいていない、甘いころになってしまう。気づいていない、小さいころの甘い世界になってしまう」
「自分が自分でいられる(幼女の)姿に惹かれた」
宮崎勤は精神鑑定の鑑定人たちとの会話で、そう何度も語っている。かれは学校を出てから就職した印刷会社をクビになり、家業の手伝いをすることに なったときに、「純粋に部屋に入りたい。社会が入ってこないところに閉じこもろう」と思った、と述懐している。宮崎勤にとって「外の世界」は、じぶんを迫 害し脅かす恐怖の対象でしかなかった。世界の何物ともかれはリンクできなかった。そのよそよそしい世界からかれを守ってくれるのは「子どものころの甘い世 界」であり、それを支えていた優しい祖父の存在だった。その祖父の死を契機にかれの暴発が始まる。いや崩落と言ったらいいか。
愉しい夢見心地のピクニック気分で山をのぼり、お菓子を食べ、「ひょっこりひょうたん島」の歌を口ずさんでから、かれは少女の頭蓋をその「おじい さんとの思い出の甘い場所」に置いて、帰ってきた。これはもう精神がバラバラになり、この世からなかば乖離した者の哀れな狂気としか思えない。(** 余 談だが、これらの宮崎勤自身が語ったストーリーは、わいせつ目的の誘拐殺人を前提とした警察の調書及び判決文では見事に無視されている)
もちろん私は宮崎勤が実際に為した所業を擁護したいわけでも軽視したいわけでもない。いたいけな幼子を4人も殺害し、その遺体を辱めた。おなじ年 頃の娘をもつ親の立場からも、ほんとうに酷たらしく、許し難いとしか言いようがない。けれど宮崎勤も、(当たり前のことだが)生まれながらの殺人者だった わけではない。むしろ犯罪を犯すまでのかれは、世の中に上手にリンクすることもその中でじぶんの居場所を見つけることもできずにいる、気弱な、コンプレッ クスに押し潰されそうになりながら押し潰されまいとかれなりに必死でもがいている、一人のおどおどとした青年であったに過ぎない。私は、かれの穴ぐらの窓 を開いてやる者は誰もいなかったのだろうか、と思う。あるいは幼少の頃、かれに世界と戯れる術を、そのわずかなきっかけでも与えてあげられるような大人は 一人もいなかったのだろうか、と思う。それが残念でならない。かれは両親をあるころから「母の人」「父の人」と呼び、ほんとうのじぶんの親ではないと信じ るようになった。
宮崎勤にとってはこの世で唯一の庇護者であった祖父が死んだ。火葬場で焼かれた亡骸を見て「あれーっ、となった。いままでの考えが180度ひっく り返る思いだった。おじいさんが見えなくなっただけで、姿を隠しているんだと強く思った」 形見分けに集まった親戚の者たちの前に立ちはだかった。「おじ いさんのものが盗まれないようにシャッターをおろした。(しかし)みな、持ってっちゃった(と涙ぐむ)。おじいさんのものは私は全然欲しくない。おじいさ んのものを盗っちゃいけない、だれも。私がもらいたかったのではない(と声を荒げる)」 祖父の部屋は空っぽになった。かれが心の拠り所としていた「甘い 場所」はこの世から完全に消え失せた。そのことをきっかけにかれは「ころっと感情を失ってしまい」、自室に閉じこもりがちになり、家族に暴力をふるうよう になった。死んだ祖父の幻を見、骨壺の遺骨を盗み食い、殺した猫を祖父の部屋に運んだ。精神がなだれを打ってバラバラと崩壊していった。
かれが最初の事件を起こすのは、その祖父の死からわずか3ヶ月後のことだ。埼玉県入間市の団地で一人で遊んでいた4歳の少女に声をかけ、車に乗せ、自宅からほど近い山道をかれはやはり甘いピクニック気分で少女と二人して歩いていく。
ピクニック気分はどんな感じなの?
「なつかしい。子どものころが思い出されて、なつかしい。自分が子どもになる」
おじいさんといっしょだったことを思い出した?
「おじいさんと山の斜面で足をのばしたり、近所の子と行ったり.... 甘い気分だった。あと、一心同体だった。私にも自分があったことがあった。その子が自分が自分である姿に惹かれた」
そのとき、時間の流れはどうなりますか?
「まわりがうすぼんやりだから、時間はゆっくりだと思う」
以前に月ヶ瀬の事件のことを調べていたとき(ゴム消し Log29)、 ある人から「殺した者も殺された者も、どちらも空しく悲しい。ただただ無明の闇が横たわっている」といったような便りを頂いた。私はこの宮崎勤の事件で も、おなじような感慨を覚え、深く息を震わせる。正直に告白するが、吉岡忍が描く被告人の生活史をともにたどりながら、私は幾度となくこの残虐な犯罪を犯 した人間の哀れな心像風景に自らのそれを合わせ鏡のように重ね合わせ、ある部分においては思わず気持ちが寄り添いはからずも共鳴することを遂に否定できな かった。宮崎勤は私とほとんど同じ世代を共有している。かれが生きた同じ時代の空気を私も同じように吸って生きてきた。ある意味でこの事件は、いまだバブ ルの祝祭に浮かれながらもこの国の全体が音もなく不気味に壊れ始めていく、そのさきがけであったような気がして私にはならないのだ。くり返すが、私は宮崎 勤が犯した酷たらしい行為も、そこに至るまでの過程も、擁護するつもりはこれっぽちもない。かれの中にそれらを自制できなかった糾弾すべき弱さも甘えも身 勝手さもまごうことなく存在し、それらはおなじように私の中にも間違いなく息づいている。無明の闇を無惨に転げ落ちながらかれが積み重ねていった行為は、 当然ながら社会的に容認されるものではないが、かれが望んでやまなかった「甘い世界」も、それらが裏切られたときに噴出するおぞましいほどの暗く絶望的な 情念も、ひとつの歪んだ極みとして私たちが生きている社会の病理を映し出しているような気がしてならない。狂気のなかにおいてさえ一抹の理(ことわり)がある。誤解を覚悟で言うならば、宮崎勤には宮崎勤なりの理があった。その身震いするような暗渠をうらうらとたどっていけば、思いもかけず私たちは、正視することも耐え難いみずからの恐ろしい裏の顔に出くわす。私は、そのように思う。
しゃべるな、語るな、沈黙するな。あの声が、また聞こえてくる。穴ぐらから出ていくことで失うものの大きさと、閉じこもることで陥る危険と、その両方を用心せよ、とその声はくり返した。閉じこもることと閉じこもらないことの中間で、この体は宙吊りになっている。
私は口ごもる。知ったかぶりの啓蒙口調に背を向け、吐き気のように襲ってくる妄想を飲み込んで、と りとめもなくつぶやいている。文章になっていかない単語の羅列。言葉にならない語尾や語頭の破片。私は口ごもり、つぶやいている。時間に追われて書き飛ば し、なにくわぬ顔でしゃべっていたときも、そんなわが身を突き放し、冷ややかに眺めているもう一人の私がいることに気がついていた。
私はみずからに言い聞かせる-----
ここが先端だ。
こここそが世界の先端なのだ。
世界はみな、いつかここに向かって殺到してくるだろう。
世界はやがて、この景色に埋めつくされるにちがいない。
21世紀はそういう世紀なのだ。
私はそう思いつづけた。薄暗くなま暖かい穴ぐらに閉じこもって、そう思ってきた。20世紀最後の10年間はずっとそんなふうだった。
私たちは世界の、憂鬱な先端にいるのだ、と。
「M / 世界の、憂鬱な先端」(吉岡忍・文春文庫)
Web上で見つけた「ひょっこりひょうたん島」の主題歌の音ファイルを私はくり返し再生し、じっと耳を傾ける。まるで救いようのないブルースのよ うだ、と思う。みずからの手で殺害し切断した少女の頭蓋をかたわらに置いて、静かな山道でこの歌をひとり孤独に口ずさんでいたとき宮崎勤は、かれはそのと きいったい何を思い、何を感じ、どんな風景を見ていたのか。その情景を思い描こうとしてみるのだが、私はそこで足踏みをしてしまう。この歌の先に、この世 界の憂鬱な先端の向こう側から、いったい何が見えてくるのか。私には分からない。分からない。
波をジャブジャブジャブジャブかきわけて
(ジャブ ジャブ ジャブ)
雲をスイスイスイスイおいぬいて
(スイ スイ スイ)
ひょうたん島は どこへ行く
僕らをのせて どこへ行く丸い地球の 水平線に
何かがきっと 待っている
苦しいことも あるだろさ
悲しいことも あるだろさ
だけど 僕らは くじけない
泣くのはいやだ 笑っちゃおうすすめ ひょっこりひょうたん島
ひょっこりひょうたん島
ひょっこりひょうたん島「ひょっこりひょうたん島」
作詞:井上ひさし/山元護久 作・編曲:宇野誠一郎
歌:前川陽子
Gregoria Allegri の Miserere のCDを聴きながら
2003.8.11 深夜
取材が深まれば深まるほど、事件は一般性から個別性へと特定されていく。そして、この先で、通俗化と、いっそうの特殊化がはじまる。
先にも述べたように通俗化は、このごろではワイドショーがやってくれる。A少年は不登校だった-- --やはり問題生徒だったのだ。彼はネコ殺しが趣味だった----やっぱりもともと残酷なやつだったのだ。あいつはホラービデオが好きだったらしい--- -なるほど、だから男の子の頭を切り落とすようなことをやったのだ。母親がきつかったという----そうか、あの家の子育てに問題があったのだ、その他そ の他。
わかりやすい解説やコメントが、視聴者をほっとさせる。事件の気味の悪さや不可解さが消えていき、 性格の悪いやつが、きわめつけの悪いことをやったのだ、というわかりやすく凡庸な解釈に流されていく。幼女連続誘拐殺害事件の判決がやってみせたことが、 ここでもっと大々的に、おおっぴらにくり返される。
そして、最後にだめ押しのように登場するのは、精神医学の専門家たちのコメントや精神鑑定書だろ う。A少年は幼児期に大切な母親との親密体験が欠如していた、攻撃性をむきだしに突出させやすい環境にあった、それが思春期に入ると性的興奮と結びつい た、直観像素質と空想癖が結合し、妄想として発展し、さらにそこに独自の狭隘な哲学が追い風となり……云々。
たしかにこれはA少年の内部で起きたドラマを理解する道筋ではある。彼の精神鑑定書は公表されているかぎりで判断すれば、細部までよく目配りされているようだし、家裁の決定要旨も過不足なくその趣旨を受け止めている。
だが、と同時に、これは彼をこの社会から切り離す作業ともなった。その内容を知れば、たいてい私た ちは、私の家族はああではないと安心し、私は、あるいはわが子は直観像素質者とかいう記憶力抜群の人間ではないとほっとし、哲学なんてややこしいものは 持っていないから、わが家は、わが子は、いや、なにより私自身が大丈夫と考える。
こうして世の中を震えあがらせた事件はA少年に特異の、彼にかぎって、たまたま彼だけがやったことになっていく。
この一連の過程こそ、私たちが事件を忘れていく過程となるだろう。事件を最初に知ったときにぞっと した不安が慰撫され、安心感におおわれていく。事態を明確化する努力はモンスターとしてのA少年像を描くことで終わり、いつのまにか関心の希薄化と忘却を 促進しはじめる。
通俗化と特殊化は本来、反発し合う関係にある。けれども、濁流のように流れるメディアの言語のなかでもみくちゃにされているうちに、両者は同じ役割を演じてしまう。これが事件の忘れられ方、忘却のプロセスとなる。
●
それからしばらくして、別の事件が起きる。
またみんながぞっとする。
が、やがてみんなをほっとさせてくれる言葉がやってきて、忘却がはじまる。
そして、それからまたしばらくして……。
そのくり返し、またくり返し。
しかし、どこにもこの、くり返し-----という現象を解く鍵がない。
「M / 世界の、憂鬱な先端」(吉岡忍・文春文庫)
ひどく疲れていて、あまり多くを書くことができない。CDの棚から古謝美佐子の「童神」をとり出して耳を傾ける。いま、私に力を与えてくれるものがあるとしたら、この歌しかないように思う。私はやっと机に向かう。
宮崎勤も神戸の少年Aも、祖父母の死を契機に精神的な不安定に陥っていることに気づいた。そして宮崎は祖父の死を契機に、神戸の少年Aは祖母の死 を契機に、小動物を殺し解剖することを始めている。この奇妙な符合はいったい何を意味するのか。両親を飛びこえて祖父母なのだ。私は、かれらにとって祖父 や祖母とは「歴史」ではなかったかと思ってみる。歴史を体現したもの・つなぐもの・共同体の名残り・消えゆく秩序、それらを肉体化したような存在ではな かったか、と。
「M / 世界の、憂鬱な先端」のなかで吉岡忍は、少年少女たちが暴発した町々を経巡り、それらどの町もが、小綺麗でのっぺらとした無個性の、奇妙に似通った新興住 宅地であったことを指摘している。以前にテレビで、アフリカかアジアかどこかの少数民族を紹介した番組を見た。かれらの住居はぐるりとつらなり、広場を真 ん中にしてきれいな円を描いていた。いわば円形の集合住宅なのだ。それはかれらの神話であり、世界観であり、メンタルな文化を表現し、内包したものだっ た。そもそも人が住まう場所とは、そのようなものではなかったかと私は思う。
体験は言葉を得て自覚化され、経験になる。
そうやって蓄積されていく経験が、少しづつ主体を作っていく。
主体がむっくりと立ち上がる。
しかし、この先になにがあるか?
私たちの前には生活圏の町が広がっている。豊かさを求めて走ってきた長い道のりの到達点、清潔さに あこがれてきた歳月の安息の地、因襲を逃れて航海してきた海路がたどり着いた明るい港。人はもう一歩、進もうとする。人はもうひと呼吸、しようとする。人 はもうひと漕ぎしようと、腕を伸ばすかもしれない。
だが、そこに、そんな人間の努力を受け止めてくれる時空間があるだろうか。ここが居場所だ。ここで自由にやっていけと励ましてくれる、あの神話のような時空間が?
主体が生きている場所の起源を教え、成り立ちを伝え、奥行きと広がりを示しているようなおおがかり なストーリー。無からはじまった主体の人生が、絆や愛といった危ういものにつながり、主体を超えた存在に助けられてかろうじて持ちこたえているのだと告げ るシンプルな物語。そういう人と人々を統合していくものが、生活圏の町にはあるだろうか。
ない----。
私はそう答える。
そういうものは、なくてもいいことにしたのだ。
それこそが私の国の歴史的制約なのだ、と。
● 神話は、人間が作った最初の文化、少なくともそのひとつだった。人々が長い歳月のあいだに作り上 げ、脚色し、枝葉を落とし、語り伝えてきた物語である。それは多分に史実ではないとしても、社会の成員のとりとめもない行為に、意味とまとまりと方向性を あたえる役割をになってきた。
島生みの話はそれを縦にも横にも広がる空間意識を示しながら、ゆるやかにやってみせていた。そこには強制力を働かせるのではなく、人をまとめ、人に居場所を教え、人に生きる方角を指し示し、あとは自由に生きていけと励ます力があった。
● 彼らはみんな関係によって壊されている。関係が切れたとき、気づくのはそのことである。集団と、集 団が作りだす現実。そこからの無言の、過剰な期待と、そこへの適応強制。生まれたときからずっと身近にあり、そういうものだと思い込んでいた関係が自分を 傷つけ、壊していたのだとわかったとき、どこにも行き場がない。
不登校、家庭内暴力、非行、引きこもり。
一人ひとりの少年少女は、個人というものが、いつも落ちこぼれやはぐれ者としてしか存在しないこの国の不幸とゆがみを背負うことになる。
どれもこれも私の国が経済大国となった以降の、国際化・ハイテク・高度情報化のかけ声すら後景に退いた20世紀最後の10年間、日本中のあちこちの生活圏の町に生きている少年少女や若者たちの姿なのである。
(吉岡忍・前掲書)
宮崎勤がアメリカとの戦争も、日本に原爆が落とされたことも覚えていなかったことを思い出そう。かれにとって歴史などというのは不必要なものだっ たのだ。それはもう死んでいるものだから。人に秩序を与え、居場所を示し、励ましてくれる生きた歴史は、もうこの国では死んでいるのだ。かれにとってリア ルなものは、だから「流行っているもの」・無限に続くビデオの収集だった。
私はいま、かつてオウムを論じた著書の中で宮内勝典が言った「意識や精神の営みに、なんらかの意味をあらしめようとしても、この社会には受け皿が ない」という言葉をあらためて思い出している。結局そこへ行き着くのだ、と私は呟く。私たちに決定的に欠けているのは“聖なるコーンミール”なのだ。
疲れ切った私はふたたび古謝美佐子の歌に耳を傾ける。「天架ける橋」のなかで彼女は、死んだ母が天へのぼってゆき、先立った夫がそこで手をさしの べて迎える様を歌っている。そしてみまかった母に天から、残る子や孫たちにどうか光を与えてください、と頼む。ここには確かな「歴史」がある。生命の豊か なつらなりがある。
それこそが私たちの社会が失ってしまったものだ。求めてやまないものだ。何も難しいものではない。単純で素朴なものだ。人間が本来、宿していた力 だ。それを私たちは、物質的な豊かさと引き替えに、いつのまにかすっかり失ってしまった。捨ててしまった。そしてたぶん、捨てたことさえ気づかずにいる。
私はそれらがあったなら、宮崎勤も少年Aも、あのようなことをしでかさずに済んだのではないかと思う。いや、断固としてそう確信する。それはもはや手遅れの、哀しい空想に過ぎないけれど。
もうすこしだけ、私は古謝美佐子の歌を聴いていよう。宮崎勤が孤独な山中で歌った「ひょっこりひょうたん島」の歌を振り払うように、何度でもくり返し聴き続けよう。そうしてまた明日から、のろのろと歩み出すための力をすこしだけ分けてもらおう。
ここが、先端だ。
世界の、憂鬱な先端が、ここにある。
おそらく私の国が歴史を取りもどすことはないだろう。この国を20世紀のまんなかで大陥没させた狂信や残酷さや激しい暴力を思い起こす記憶力を、この社会は持っていない。解離はまだつづいている。それが、私の判断である。
そうであれば、ひとつの国が、ひとつの社会が、一人の人間が持っている攻撃性の意味を考え、想像 し、認識するのは一人ひとりがやるしかない。集団にたよらず、一人で考え、あたえられた関係を離れ、絆を選びなおし、そうやって親密圏を作っていくなかで 人間と国家と世界の善と悪を、正と邪を、愛と憎を、美と醜を、真と偽を見きわめ、もう一度理念を作っていくこと。
しかし、歴史認識を欠いたまま理念を作ることができるだろうか?
たとえできたとしても、それは脆弱なままではないだろうか?
そうかもしれない、と私も思う。
だからこその先端なのだ。
やがて確実に歴史を忘れていく世界の、憂鬱ではあるけれどもここが先端なのだ。
私たちは陰惨な事件のたびに驚いているわけにはいかない。メディアの言語に圧倒され、右往左往して いるばかりでは、一歩も進めない。妄想と攻撃性が結びついたとき、人は、国家や世界と同じように、どんな残酷なこともやる、やってのけるというリアルな感 覚を一方に置きながら、私たちは希望を語らなければならない。
昔の人なら、その全体を神話と呼んだだろう。
私たちは世界の、憂鬱な先端で新しい神話を語ることができるだろうか。
いつか私も神話を語ること、それが21世紀に持っていく私自身の夢である。
(吉岡忍・前掲書)
2003.8.12
宮崎勤の魂はあの世で救われるだろうか、と考えてみる。かれに殺された少女たちのちいさな魂はあの世で救われただろうか、と考えている。テレビを つければ、あの汚いイラク戦争に早々と同調したこの国の首相とやらが「戦争で亡くなった尊い人命に哀悼の意を表します」なぞと臆面もなく喋っている。私た ちの国は、ひどくさみしい国になってしまった。嘘ばかりだ。嘘ばかり。
今日も一日、馬鹿どもの車を誘導してから、帰って古謝美佐子の「童神」を相変わらず聴き続けている。何かが溢れ出てきそうになるのだが、じぶんはそれに値しないと思う。
私たちの全員があの少女たちを無惨に殺し嬲ったのだ。私たちの全員が宮崎勤をあのような場所に追い込んだのだ。私たちこそが彼らの宿主(しゅくしゅ)だ。
2003.8.15
■体感する